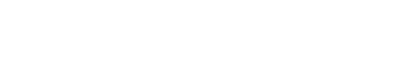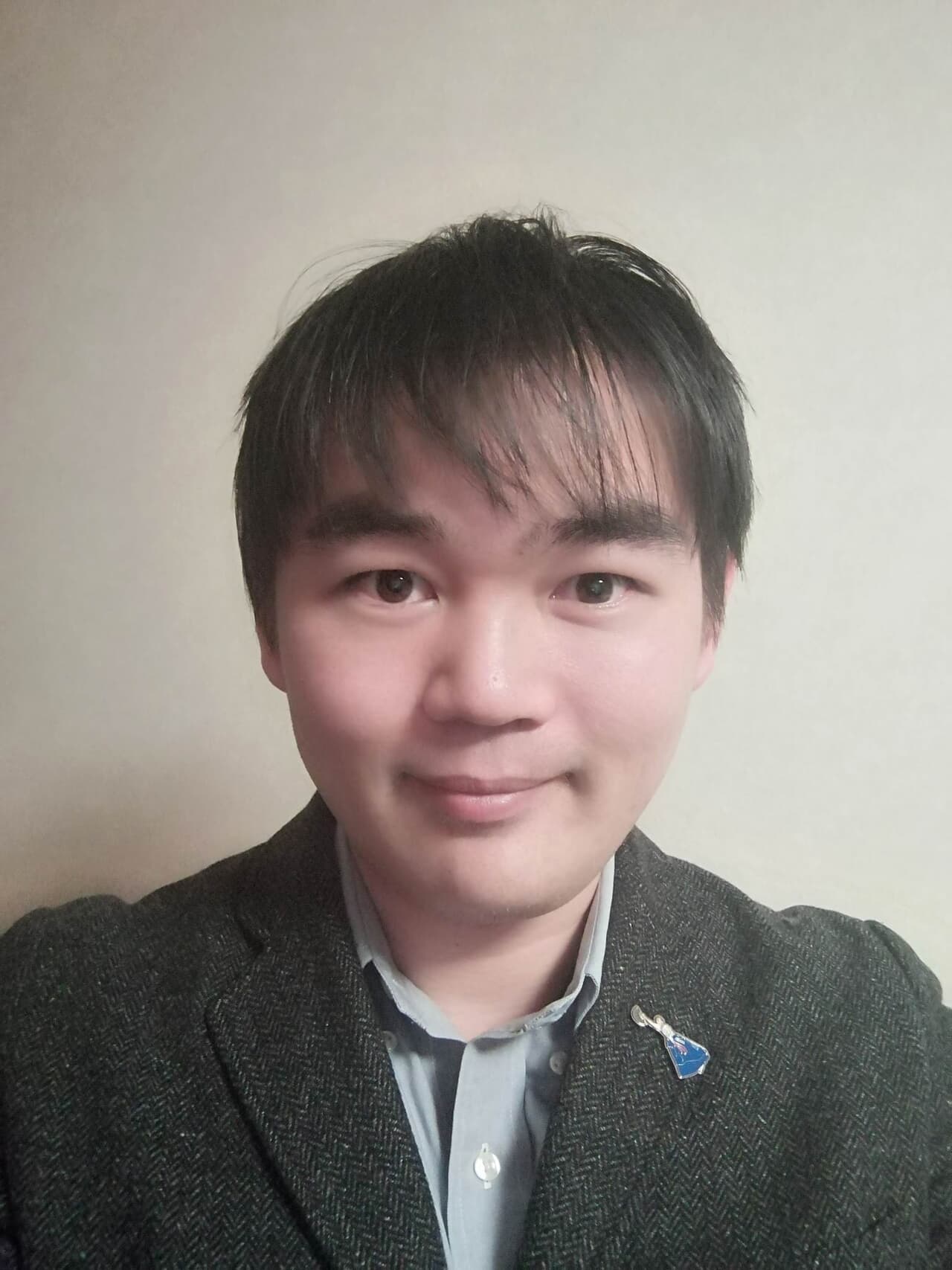思想家としての「小沢健二」入門
■「手仕事を大切にすること」
それでは小沢健二は、何を「善いこと」だと考えているのか。
彼が2000年代後半から発表してきた物語やエッセイにはその答えが具体的に書かれているのだが、楽曲の歌詞にもそのエッセンスは見え隠れしている。例えば2012年の「東京の街が奏でる」コンサートで発表され、後に音源化された「神秘的」では以下のように歌われていれる。
「幻? いや それはイスラム教の(2番では「キリスト教の」)詩(うた)のように 確かな時を刻むよ(2番では「愛という奇蹟を讃うよ」)」
「幻? いや それは台所の音とともに 確かな時を進むよ」
「神秘的 でも それは台所の歌とともに 確かな時を遠く照らす」
(「神秘的」)
つまり小沢健二は、イスラム教やキリスト教の祈りの詩と、台所の音(歌)は、同じように神秘的だと評価しているのだ。私の解釈によれば、台所の音は「超越的な善の視点」に適うということだろう。
「流動体について」「神秘的」を含め、活動再開後に発表された多くの曲が収録された2019年のアルバム『So kakkoii 宇宙』(英題:So kakkoii Pluriverse)では、この思想がさらに明確に打ち出されている。
オープニングナンバーの「彗星」では
「今ここにある この暮らしこそが宇宙だよと 今も僕は思うよ なんて奇跡なんだと」(「彗星」)
と「暮らし」という言葉をフィーチャーしており、最後を飾る「薫る」では
「君が君の仕事を(2番では「学業を」)する時 偉大な宇宙が 薫る」(「薫る(労働と学業)」)
と、仕事(労働)と学業を賛美している。
つまり小沢健二は、仕事や学業で構成された日々の生活を「善いもの」として捉えているのだ。ある時から小沢健二は、コンサートの最後にカウントダウンし、(エンターテインメントという非日常から)「日常に帰ろう」と締めるようにもなっている。
それでは小沢健二は、「何でもいいから働け」というブラック企業の経営者みたいなことを言っているのかというと、まったく真逆だ。
2016年に発表された「仕事をせんとや、生まれけむ」という朗読台本の中で、小沢健二は「人には、仕事をしたいという性質が備わっている」が、「与えられた仕事が、したくない仕事だから」(人はサボる)という研究結果を紹介し、「社会にある仕事は(中略)」、例えば数字を動かすだけのような「手で触れられないものになった」ことに言及している。その結果「「嫌だなあ、仕事したくないなあ」と思っているとしたら、僕は、やっぱり、したい仕事が多い世の中になればいいなあ、と強く願う。」と語っている。(本段落のカギ括弧内は「仕事をせんとや、生まれけむ」(小沢健二、2016)より引用)
手で触れられる、私の生活から離れない、「したい仕事」。それが小沢健二にとっての「善いこと」なのだろう。
カール・マルクスは、資本主義により人は世界との交感を妨げられ、疎外されていることを看破し、労働者の団結を呼びかけ共産主義の到来を予言した。
小沢健二は、やはり資本主義が人と世界の交感を妨げていることを問題視したが、「だったらこっちからさっさと世界と交感すればいいじゃん」という、より直接的、かつ一人ひとりが個人的に実現可能な方法を提案した。それが宇宙を薫らせる、善いことなのだと。
日常のために作られた道具の中に阿弥陀仏の業を見出し、「民藝」と名付けた柳宗悦のように、小沢健二は日々の生活の中に神秘的なものを見出した。その結果ツアーグッズなんかもオザケン自身がデザインするようになった。
この思想が前面に顕れているアルバム『So kakkoii 宇宙』の英題では、「宇宙」という単語が一般的に使われる「Universe」ではなく「Pluriverse」と訳されている。
「Uni」=「ひとつの、統一された」宇宙ではなく、「Pluri」=「多量の」宇宙、よく聞く言葉で言えば「多元宇宙」ということになるだろう。
しかし、これまで解説してきたような小沢健二思想を吸収してきた私は「一人ひとりの宇宙」と理解するのがより適切だと思える。かつて「神は死んだ」と宣言したニーチェが、後になってツァラトゥストラの口を使って「死んだのは「唯一」を名乗る神であり、一人ひとりが頂く神は生きている」と訂正したように。ニーチェの言う「超人」とは、言い換えると人間が「一人ひとりの神」になることを目指す途上にいる半神のことだ。
■すべては小沢健二への「推し活」である
とまあ、ここまで駆け足で、私の思想の小沢健二からの影響を紹介してきたが、要ははじめに提示した「温故知新」「信仰を軽んじないこと」「手仕事を大切にすること」が、私が小沢健二から受け取った思想だ。
こうして自分の思想の形成過程を振り返ってみると、はじめに私の趣味として挙げたコーヒーを淹れることも(結果喫茶店のマスターをやってみたことも)、能を習っていたり、数学を勉強してみたりしたことも、演劇に参加していることも、すべて「小沢健二から受け取った思想の体現」だったことに今更ながら気がつく。私の中の小沢健二が、私をして「喫茶店やりませんか?」という誘いに「YES」と答えせしめ、習い事として能を選ばせしめたのだ。
だとしたら、キリスト者が人生をキリストへの捧げ物にするように、私はオザケン者として人生をオザケンへの捧げ物にしてきたと言って過言ではないし(過言ではないにせよ、強引だとは承知しています)、その態度はたしかに私自身の人生を彩り豊かにしてきた。
SHIBUYA TSUTAYAで『カメラ・トーク』を手に取ったあの日から、私は小沢健二への「推し活」としての人生を送ってきたのだ。
文:甲斐荘秀生